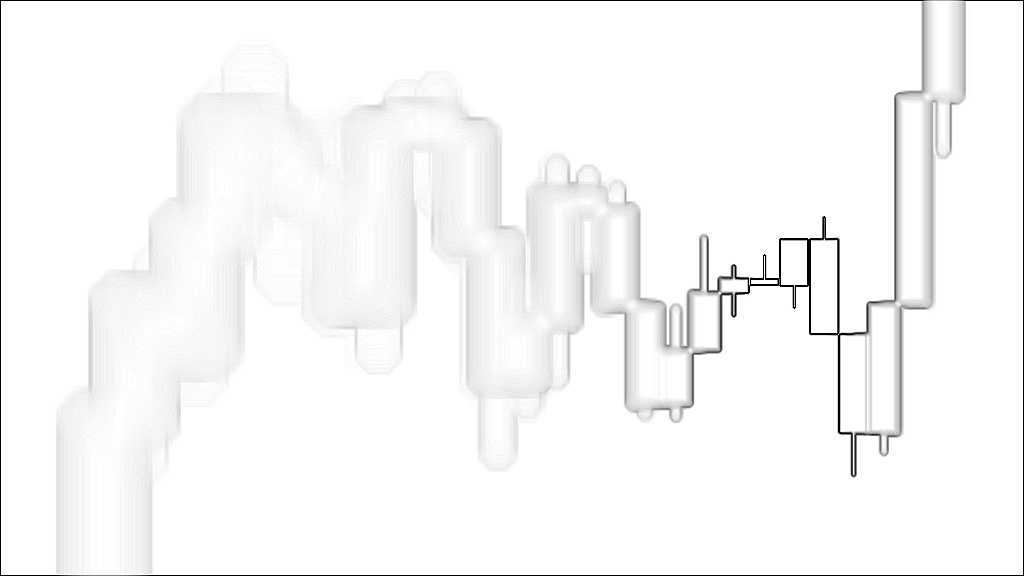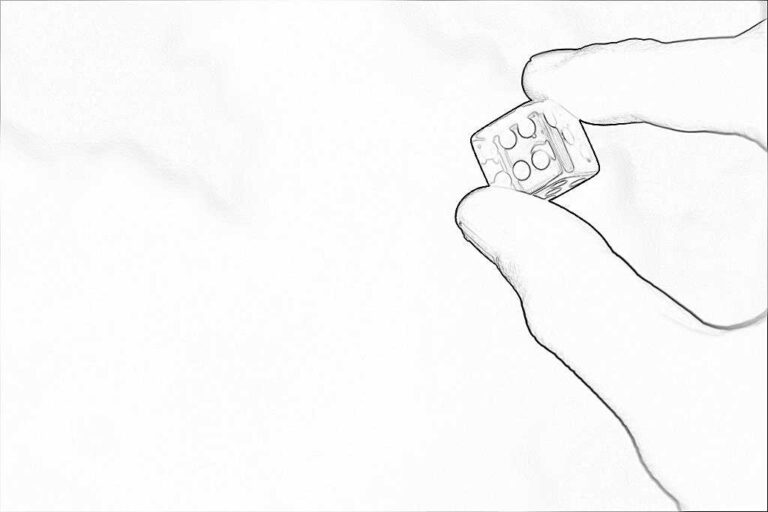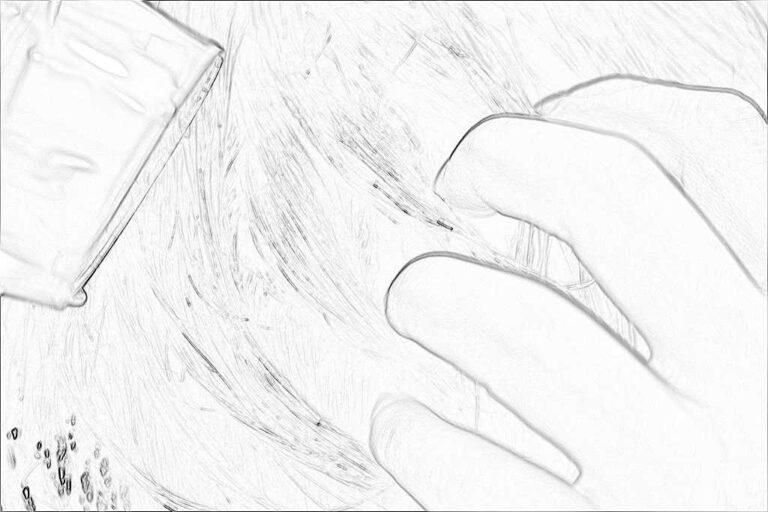黒背景に浮かび上がるローソク足チャートが、ひときわ大きな陽線を描いた。
ニューヨーク市場の終値、+3.1%。彼の投資判断は当たった。だが、喜びの実感はなかった。
天野 慎(あまの しん)は32歳、都内の外資系証券会社でファンドマネージャーを務めている。
複数の富裕層から預かった総額数十億円の資産を運用する日々。チャートの乱高下とニュースの嵐に目を凝らし、秒単位で利益を追い求める仕事だった。
「やっぱりさ、為替が一番動きやすいんだよ。株よりよっぽど収益効率がいい」
同僚たちとの昼食も、話題は相場と収益の話ばかり。
デュアルディスプレイには常に色とりどりのカラフルなグラフが描かれ、赤や緑の値動きが乱舞する。天宮はそれを冷静に見ながらも、心のどこかに空虚さを感じていた。
「金曜決済、やっぱ正解だったな……」
得意先の顧客から送られてきたメッセージに、彼は自動的に「はい」とだけ返した。
その週末。
少し疲れを感じた天野は、都心から1時間ほど離れた里山の麓へと足を運んだ。中学生のころまで祖父が住んでいた場所だ。久々に心を無にしたくなった。
駅から続く農道を歩いていると、道端で息を切らし、タンクを抱えた老人に出会った。
そういえば、晩年の祖父もよく腰が痛いと言っていた。丈夫な体だけが俺の取り柄だと口癖だったあの祖父のシルエットが、どんどん小さくなって行った光景と重なる。なんだか声をかけずにはいられなかった。
「大丈夫ですか? それ、持ちますよ」
驚いた表情を浮かべたその老人は、しばし躊躇し、やがてふっと笑った。
「そりゃ助かる。もうこの歳じゃ、草刈機の燃料でも重労働でね」
タンクを軽々と持ち上げる天野に、老人は申し訳なさそうに頭を下げた。家はすぐそこだった。小さな平屋、裏には手作りの畑。
「ここで野菜を作ってね、地元の商店に少し卸してる。まあ年金暮らしの暇つぶしみたいなもんさ」
老人の名は 篠原 源一(しのはら げんいち)。昭和の終わり頃までは機械工場の職人だったという。
「豪華な暮らしはできんが、食うもんは自分で作れるし、こうして誰かに助けてもらえる。不思議と寂しくはないんだ」
天野はなぜか、その言葉に胸を打たれた。
帰り際、源一が段ボール箱に入れて持たせてくれたのは、畑でとれたばかりのナス、トマト、そして土の香りのするきゅうりだった。
「いくらですか?」と天野が尋ねる。
源一は「金はいらないから、持っていけ。」と、大きく首を横に振ったが、どうしても購入したいと思った。なぜか、どうしても支払わせてほしいと強く感じた。
「んー、じゃあ500円でどうだい?お金をどうしても払いたいって、そんなに必死に頼み込んでくる人は初めて出会ったなぁ。 」と笑う源一。
丁寧に紙袋に入れられた野菜を受け取ったとき、天野はなんだか「このやりとり」こそが、本当の価値交換なのではないかと感じられた。
帰りの電車。スマホでチャートを確認する手が止まり、彼はスマホをバッグにしまった。
翌週、天野はデスクでチャートを見ながらも、心はどこか穏やかだった。ローソク足が下ヒゲを引こうが、レンジ相場になろうが、彼の中の「何か」が確かに変わっていた。
顧客の損益報告を終えたあと、彼はふと手帳を開き、一言だけメモに書き残した。
「金融市場はコントロールできなくても、心のチャートは自分で右肩上がりにできる」
あの畑のきゅうりは、少し歪んでいた。でも、かじると青い香りが口いっぱいに広がり、少年時代に祖父と一緒に食べたあの夏の日を思い出させてくれた。
もう一度、週末に源一の家を訪ねてみようと思った。野菜を買うためではない。ほんの少しだけ、心を耕しに。
もし明日に大暴落が来ても、人生の本当の価値が失われるわけじゃない。
幸せとは、静かで、そして確かな実感の中にある。

HiStory[単行本]
HiStory「シーズン1」から「シーズン4」までのお話を収録した単行本を注文できます。
完全オリジナル、完全受注生産。
ここでしか入手できない創作小説。旅のお供に持って行ったり、夜の静かな自分時間にお楽しみいただける一冊に仕上げました。
紙の本だからこその永久保存版として、ぜひあなたのライブラリーに追加してください。