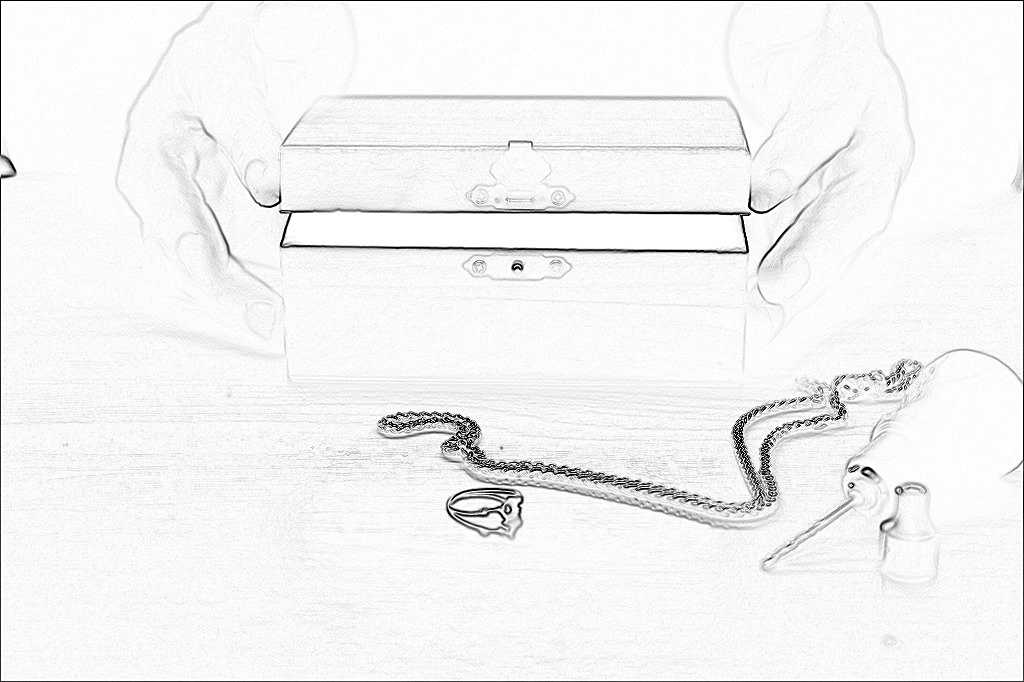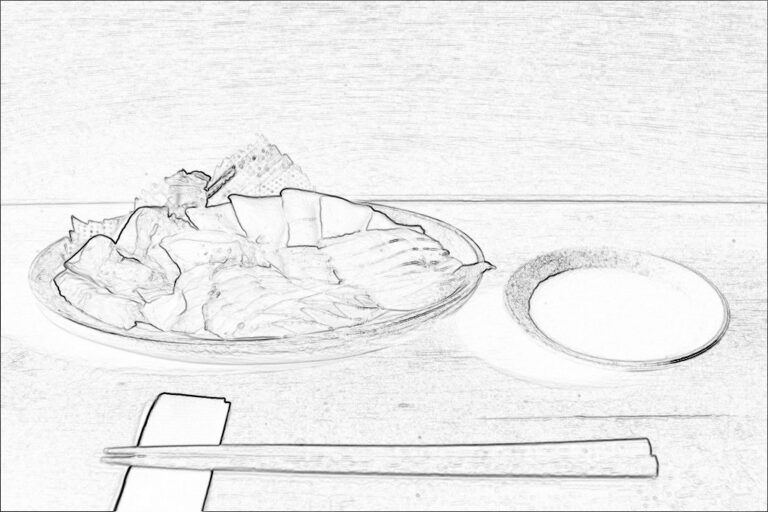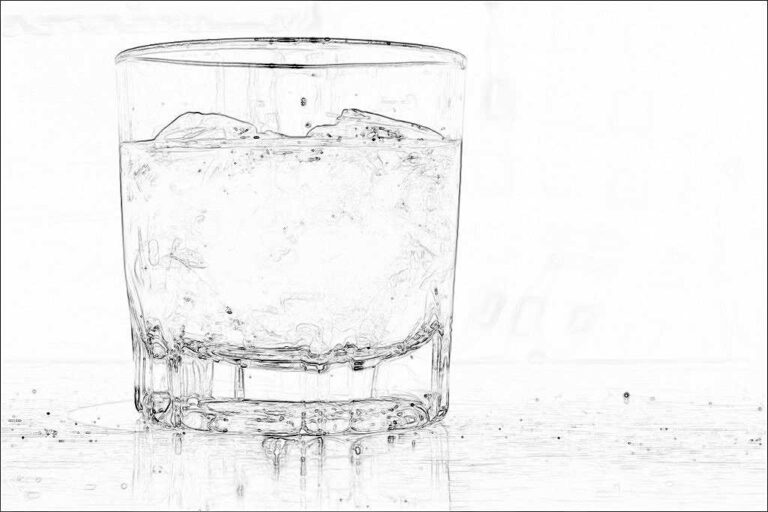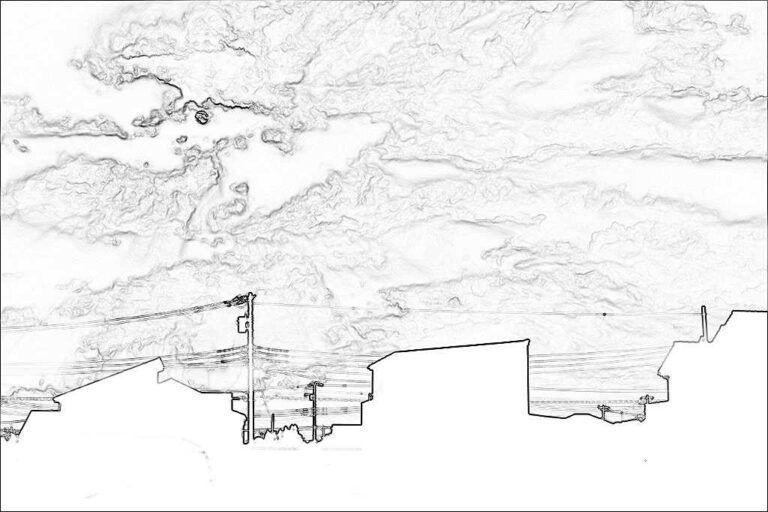人であふれた駅前のロータリーを歩きながら、翔太はふと足を止めた。
夕方の街は、まるで自動的に動き続ける巨大な機械のようだった。スーツ姿のサラリーマンが無言で改札へ吸い込まれ、制服の学生たちはスマホ画面を睨みながら友人と笑い合っている。カフェの前ではイヤホンを耳に差した若者が立ち尽くし、片手の親指だけがせわしなく動いていた。
どこを見ても人、人、人。だが、そのざわめきは奇妙なほど自分の心に届いてこない。笑い声も会話も耳に入っているはずなのに、まるで壁一枚隔てた別世界の出来事のようだ。
――これほど大勢の人間がいるのに、誰ともつながっていない。
そんな感覚が、ここ数年で強まっていた。
職場で同僚と休憩中に世間話をしても、すぐに話題は途切れてしまう。昔なら「昨日のテレビ見た?」という一言で盛り上がれたのに、今は誰も同じ番組を見ていない。音楽を聴くにしても、それぞれが違う配信サービスで、違うジャンルを追いかけている。
学生の頃は、流行りのゲームやアニメの話題で自然に笑い合えた。放課後の教室に残って、攻略法を語り合ったり、キャラクターのセリフを真似して笑ったり――あの頃は、「同じものを知っている」というだけで友達になれた。けれど今は、会話を始めても、相手がそのコンテンツを知っている保証はない。みんなが各々のアプリを開き、各々の動画を追いかけ、まるでバラバラの小舟で同じ海を漂っているようだ。
言葉は届くのに、心は交わらない。
残されるのは、話題が交わらない空白だけ。沈黙を埋めるために、誰もが再びスマホに視線を落とす。
「寂しい時代だよな……」
つぶやきは、ロータリーを横切るタクシーのクラクションにかき消され、誰の耳にも届かなかった。翔太自身でさえ、その言葉を本当に自分が口にしたのか確信を持てなかった。
週末、翔太はなんとなく遠出をした。特に目的があったわけではない。電車に揺られているうちに、ふと「このままどこかへ行ってしまいたい」という衝動に駆られたのだ。都会のざわめきから少し離れたくなった。
小さな郊外駅で降りると、商店街のシャッターが目立つ通りに出た。空き店舗の壁に、一枚の色鮮やかなポスターが貼られている。「夏祭り ○月○日 午後六時~」。翔太は足を止めた。
――祭りなんて、子どもの頃以来だな。
その懐かしい響きに胸を引かれるようにして、ふらりと足を運んでみることにした。
夕暮れの境内に近づくと、すでに提灯の灯りが点されていた。赤や橙の光がぼんやりと揺れ、境内全体を温かく包み込んでいる。焼きそばの香ばしい匂い、金魚すくいの水面を跳ねる音、射的台から響くコルクの破裂音。それらが混ざり合い、街の静けさとは違う「生きている音の洪水」がそこにあった。
浴衣姿の子どもたちは走り回り、はしゃぐ声が夜空に弾む。屋台の前で立ち止まる親子、ビール片手に笑う大人たち。みんなが同じ場所で、それぞれの楽しみを見つけている。翔太は思った。
――ここには、スマホの画面越しでは届かない、ひとつの「空気」がある。
やがて櫓の上に太鼓が据えられ、低く響く音が夜を震わせた。太鼓の合図に合わせて笛と三味線が加わり、輪の中で人々が踊り出す。見知らぬ人々が、自然に手拍子を揃え、足を運び始める。
翔太は最初、境内の隅に立ってその様子を見ていた。都会で育った自分には、こうした光景はどこか場違いな気がしたのだ。けれども、踊りの輪はゆっくりと広がり、気づけばすぐそばまで迫ってきていた。
「ほら、あんたも入んなさいよ」
隣にいた年配の女性が笑顔で手を伸ばしてきた。抵抗する間もなく、ぐいと腕を引かれる。気づけば翔太は輪の中に放り込まれていた。最初はぎこちなく見様見真似で手を叩き、足を動かす。それでも周囲の人々は、そんな不格好さを笑うどころか、にこやかに頷き合っている。
やがて自然と体が動き出す。リズムに身を任せているうちに、見知らぬ隣人と目が合った。互いに照れくさく笑う。ほんの一瞬のことなのに、心の奥が温かくなるのを翔太は感じた。
――ああ、これが「共通体験」ってやつなんだ。
誰もが同じ音を聞き、同じ動作を繰り返し、同じ夜を過ごしている。ここでは「あなたは何に興味があるの?」と確認し合う必要なんてない。ただ隣り合う存在として、同じリズムに揺れていれば、それだけでつながれるのだ。
帰り道、夜風に吹かれながら歩いていると、ふと子どもの頃の情景が脳裏に浮かんだ。
まだ小学生だったあの頃、クラスの友達の家に集まって、ファミコンの電源を入れる瞬間の高揚感。カートリッジを差し込む音、画面に現れるタイトルロゴに歓声を上げたこと。コントローラーは二つしかないから、勝った者が残り、負けた者は順番待ちをしながら観戦する。誰かのプレイを見て、みんなで一喜一憂した。
翌日の学校では、クラス全員が同じテレビ番組を見ていた。昨夜のバラエティ番組のギャグを真似するだけで教室中が笑いに包まれる。人気ドラマの展開をめぐって真剣に語り合い、好きな歌手の新曲が出れば、休み時間に校庭で大合唱になった。あの頃は、文化が「みんなの言葉」として街を満たしていた。誰もが同じ川の流れに身を任せ、その水の冷たさや速さを確かめ合っていたのだ。
今は違う。
世界中の音楽や映画を、指先ひとつで選べる。確かにそれは便利だし、選択肢の多さはかつてない自由を与えてくれる。けれどそれは、同時に「無限の選択肢という名の孤独」でもあった。無数の流れに分岐した川のどこを選んでも、隣に同じ景色を見ている人がいるとは限らない。
誰もが違う部屋で、違う画面を覗き込み、違うリズムで時間を過ごしている。
本来なら「人とつながる」ために生まれたはずのテクノロジーが、むしろ人を細かく分断し、それぞれの小さな孤島へと押しやってしまった。
だが、さきほど祭りの輪の中で感じたあの温度は、そんな思い込みを崩した。デジタルが悪いわけではない。ただ、それだけに偏ってしまうから虚しさが生まれるのだ。画面の中で完結させるのではなく、たまには現実の空気に身を置く。人の声や匂い、触れ合う瞬間を分かち合う。そのバランスがあってこそ、人は文化を「共有」できる。
提灯の残像がまだまぶたに揺れている気がした。胸の奥に小さな確信が芽生え、それは夜風に冷やされながらも、不思議なほど温かく翔太の中に灯っていた。
翌週、翔太は昼休みにふと思い立ち、隣の席の同僚に声をかけてみた。
「この前、夏祭りに行ったんだ。意外と楽しくてさ」
唐突な話題に、同僚は一瞬きょとんとした顔をした。
「へえ、そんなのまだあるんだな」
軽く笑って返してくれたが、それ以上の広がりはなかった。次の瞬間にはスマホの画面に視線を落とし、話題はあっけなく途切れてしまった。
ほんの少しの落胆が胸をかすめた。だが、すぐにそれを押しのけるように、あの祭りの光景がよみがえる。提灯の灯り、太鼓の音、知らない人と自然に笑い合った瞬間――。
翔太の心には、小さな確信が芽生えていた。
――この街のどこかに、まだ「つながれる場」は残っている。
誰かと一緒に息を合わせられる時間が、きっとひっそりと息づいている。それを探しに行けばいい。ただ待つのではなく、自分から足を運べばいいのだ。
夜、退勤後の風に吹かれながら、翔太は駅前の人波に身を投じた。人々は相変わらずスマホを見つめ、画面の光に顔を照らしている。けれど、翔太の胸の奥には目に見えない糸のようなものが残っていた。祭りの輪で感じた温度が、まだそこに灯っている。
孤独に満ちていたはずの街が、ほんの少しだけ柔らかく感じられた。
それは幻かもしれない。けれど、翔太にとっては十分だった。
足取りは不思議と軽く、彼は群衆の中を静かに歩き出した。